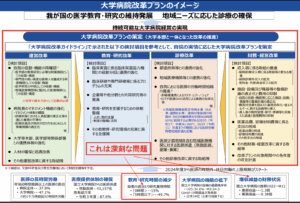皆様こんにちは。島根大学の坂口公太です。
GRIPS研修3日目。これまでの歴史や政治といった文脈から一転し、本日は「医療経済学」という、また新たなレンズを通して医療制度を眺める一日となりました。臨床医として目の前の患者さんを救うことを第一に考えてきた身からすると、時にドライで、しかし極めて重要なこの視点は、多くの思考の揺さぶりをかけてきました。
「良いこと」は、必ずしも「安上がり」とは限らない
今日の講義で最も衝撃的だったのは、「予防医療が、必ずしも医療費の抑制に繋がるわけではない」という事実です。
私たちは素朴に「病気を未然に防げば、将来かかる医療費が減るはずだ」と考えがちです。しかし、経済学的な評価はもっと厳密です。予防医療は、その効果と費用に応じて、以下の3つに分類されると学びました。
Cost-saving(費用削減型): 予防にかかる費用以上に、将来の医療費を削減できる。
Cost-effective(費用効果的): 費用は増えるが、それに見合うだけの健康アウトカム(寿命の延長など)の改善が見込める。
Cost-ineffective(非費用効果的): 費用がかさむばかりで、効果が薄い。
そして驚くべきことに、数ある予防医療の中で、純粋に「Cost-saving」となるものは全体の約20%に過ぎないというのです。
もちろん、これは予防医療の価値を否定するものでは全くありません。むしろ、その多くは「Cost-effective」、つまり社会の財産である国民の健康を守り、向上させるための「価値ある投資」なのだと理解しました。政策を考える上では、この「コスト抑制」と「価値ある投資」を冷静に見極める視点が不可欠なのだと痛感しました。
保険制度を動かす「見えざる手」
次に、医療保険という制度がなぜこれほど複雑な設計になっているのか、その経済学的な基本原則を学びました。特に重要なのが、「逆選択」と「リスク選択(クリーム・スキミング)」という2つの概念です。
逆選択 (Adverse Selection): 保険を最も必要とする人(=病気になるリスクが高い人)ほど保険に加入したがり、結果として保険財政が悪化する現象。
リスク選択 (Cream Skimming): 保険者が利益を最大化するため、保険にあまりかからない人(=健康な人)ばかりを選んで加入させようとする現象。
民間保険に任せると、この2つの力学によって、本当に保障が必要な人が弾かれてしまう可能性があります。だからこそ、日本が国民皆保険という「強制加入」の社会保険方式をとっていることの重要性が、理論的にも深く理解できました。
政策ツールとしての「診療報酬」
最後に、Day1でも学んだ「診療報酬」が、政策ツールとしていかに精巧にデザインされているかを学びました。診療報酬は、以下の3つの機能を通じて医療機関の行動を誘導します。
規制: 医療行為のルールを定める。
経済的インセンティブ: 点数を高く設定することで、国が推進したい医療(在宅医療など)へ誘導する。
情報の提供・誘導: 新しい評価項目を作ることで、国が重視する医療の方向性(質向上など)を現場に示す。
歴史、政治、そして経済。研修が進むにつれて、多層的な視点が積み重なり、日本の医療制度という巨大なシステムが、より立体的に見えてきました。明日もこの知的な探求を続けたいと思います。