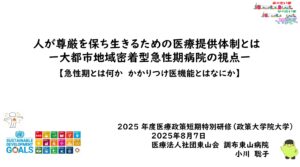GRIPS研修も佳境に入り、本日は「看護」という、医療提供体制の根幹をなすテーマに多角的に向き合う一日となりました。齋藤訓子先生によるマクロな看護政策、角田正雄先生によるミクロな経営戦略、そして角田直枝先生による臨床現場からの看護管理実践。この3つの講義が一本の線で繋がり、私の地元・島根が抱える看護師不足という課題への、新たな視座を与えてくれました。
データが示す、島根の厳しい現実
まず齋藤先生の講義で示されたデータは、衝撃的なものでした。島根県は、就業看護師に占める55歳以上の割合が全国で2番目に高く 、一方で有効求人倍率は常に全国平均を上回る「超・需要過多」の状態にあるのです 。これは、近い将来の大量退職と、深刻な後継者不足という、厳しい未来を示唆しています。
「働き方」から「働きがい」へ
では、この構造的な課題にどう立ち向かうのか。角田正雄先生の講義は、そのヒントを与えてくれました。これからの時代に人材を確保・定着させる鍵は、単なる「働き方改革」ではなく、職員一人ひとりの「働きがい改革」、すなわちエンゲージメントの向上にある、というのです 。
特に、キャリアパスの選択肢が限られがちな地方の病院において、看護師が専門職として成長を実感できる教育体制(クリニカルラダーなど)をどう構築するか。これは、若手看護師の県外流出を防ぐための、経営における最重要課題の一つだと痛感しました。
「元気になる看護管理」という希望
そして、本日最後の角田直枝先生の講義は、この「働きがい」を現場でどう実現するかの、具体的な実践例でした。先生が提唱される「元気になる看護管理」は、看護師が単に指示を待つのではなく、自ら患者の問題解決に介入し、その人らしい生活を取り戻す支援をする、極めて主体的な看護の姿です 。
例えば、高齢の救急リピート患者に対し、看護外来が介入することで再受診率を劇的に低下させた事例 や、多職種連携を通じて患者の生活全体を支援する「元気になるシステム」の構築 は、看護師の専門性を最大限に発揮させることが、患者のアウトカムを改善し、結果として病院経営にも貢献することを見事に証明しています。
これは、看護師に「あなたたちが病院を変える主役なのだ」という強いメッセージと「働きがい」を与える、素晴らしいマネジメントだと感じました。
結論:看護師不足への新たなアプローチ
本日の学びを総合すると、島根の看護師不足という課題に対するアプローチが見えてきます。それは、単に行政がトップダウンで対策を講じるだけでなく、
各病院が経営戦略として「働きがい改革」を断行し、
看護師一人ひとりが専門性を発揮して「患者を元気にする」成功体験を積める
という、ミクロな現場レベルでの変革を同時に起こしていくことです。
「看護管理」が変われば「看護師」が変わり、「看護師」が変われば「病院」が変わり、ひいては「地域医療」が変わる。その力強い可能性を確信した一日でした。