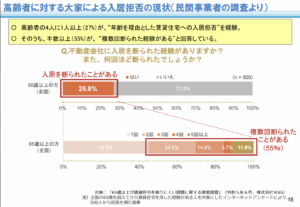GRIPS研修も最終週、本日は元厚生労働省健康局長の矢島鉄也先生から、「疾病予防と医療費適正化、データヘルス」という、まさに国の医療政策の根幹をなすテーマについて学びました。なぜ国はこれほどまでに「健康寿命の延伸」を掲げ、特定健診(いわゆるメタボ健診)の実施率を競わせるのか。その背景にある国の強い危機感と、政策のリアルな姿が見えてきた一日でした。
政策の原点にある、静かなる危機
講義の冒頭で示されたのは、日本の厳しい未来を映し出す人口推計のグラフでした。2070年には総人口が8,700万人にまで減少し、そのうち約4割を65歳以上の高齢者が占める 。一方で、社会を支える生産年齢人口は、現在の6割弱から約5割にまで減少します 。
この「支え手が減り、支えられる人が増える」という構造的な危機こそが、国が「人生100年時代」や「生涯現役」を掲げ、少しでも長く健康でいてもらうことで社会保障の持続可能性を保とうとする、全ての政策の原点なのだと痛感しました。
国はいかにして「健康」を政策にするのか
この大きな目標を達成するため、国は「高齢者の医療の確保に関する法律」などの法制度を整備し、具体的な政策ツールを動かしています。
医療費適正化計画: 都道府県が、国の基本方針に基づき、医療費の目標や、そのための具体的な施策(健診の推進、後発医薬品の使用促進など)を定める計画です 。
特定健診・特定保健指導: 40歳から74歳までを対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診と保健指導を行う、まさに予防政策の中核です 。
保険者努力支援制度: 各保険者(市町村など)の特定健診実施率などの取り組みを点数で評価し、その成績に応じて交付金を配分する仕組みです 。これにより、自治体間の競争を促し、取り組みを強化させようというインセンティブ設計になっています 。
「実施率」競争への違和感と、科学的根拠の壁
講義の中で、講師の先生が都道府県別の特定健診実施率のグラフを示し、「頑張っている自治体とそうでないところがわかる」と話された場面で、私は正直なところ、強い違和感を覚えました。
行政を「やりっぱなし」にせず、アウトカムを重視するというお話には賛同します。しかし、私の記憶では、日本の特定健診が、脳卒中や心筋梗塞を減らすといった最終的な健康アウトカムを改善するという、強い科学的根拠はまだ確立されていなかったはずです。
実際に、講義資料の中でも示されていたように、特定保健指導の効果は、体重やHbA1cといった中間指標をわずかに改善するに留まり、血圧やコレステロールには有意な差が見られていません 。
「実施率」というプロセス指標を上げることが目的化し、その先にあるべき「国民の健康」という真のアウトカムに本当に繋がっているのか。このギャップこそ、今の予防政策が抱える大きな課題ではないかと、改めて考えさせられました。
新たな視点:高齢者の「フレイル予防」
一方で、希望を感じる議論もありました。高齢者の保健事業においては、単なる生活習慣病対策だけでなく、心身の虚弱を意味する「フレイル」を予防するという、より包括的な視点が重視されるようになっている点です 。
これは、医療(保健事業)と介護(介護予防)が一体的に実施され、栄養・身体活動・社会参加という3つの柱で高齢者の生活機能を維持・向上させようというアプローチです 。単一の疾患リスクを見るだけでなく、高齢者の生活全体を支えようとするこの考え方にこそ、これからの地域包括ケアのヒントがあると感じました。
国の政策の壮大なロジックと、その根拠となるデータの限界。その両方を学んだことで、現場の医師として、国が推進する事業に協力しつつも、常にその目的と効果を批判的に吟味し、より良い形を模索していくことの重要性を再認識した一日でした。