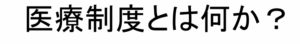皆様こんにちは、島根大学の坂口公太です。
GRIPS医療政策短期研修、2日目。今日は思い切って宿舎のある立川から六本木のキャンパスへ。やはり、他の参加者の皆さんの熱気や、休憩時間の何気ない会話の中に身を置くと、学びの深さが一層増すように感じます。
初日が日本の医療制度の「基本構造」を理解する日だったとすれば、2日目の今日は、その制度の中に存在する「多様性」と「複雑さ」の源流をたどる一日でした。
医療の「県民性」は、戦後の“選択”で決まっていた
昨日の講義で学んだ「経路依存性(Path Dependence)」という概念が、今日はさらに具体的な姿をもって目の前に現れました。テーマは「なぜ、県によって医療提供体制はこれほど違うのか」。その答えは、遠い戦後の歴史の中にありました。
講義で示されたのは、秋田・岩手・青森の3県の事例です。戦前、地域医療の一端を担っていた産業組合の診療所が、戦後のGHQによる組織解体を機に、それぞれ異なる組織に引き継がれました。
秋田県 → 厚生連(農業協同組合厚生連)が継承
岩手県 → 県が継承(買収)
青森県 → 市町村が継承
この、たった一度の歴史的な分岐点が、70年以上経った現在の医療地図を決定づけています。秋田では今も厚生連病院が地域医療の中核を担い、岩手では県立病院が、青森では市町村立病院が非常に多い。それぞれの県が持つ医療の「個性」や「文化」は、こうした歴史的背景によって形作られていたのです。
この視点を持つことで、例えば私のいる島根県の医療課題を考える際にも、「なぜこのような提供体制になっているのか」という歴史的文脈を抜きにしては、本質的な議論はできないのだと痛感しました。
一枚岩ではない、医療界のステークホルダー
もう一つの大きな学びは、医療政策の決定プロセスにおける「アクター(関係者)」の多様性です。
私たちはつい、「医療界の意見=日本医師会(日医)の意見」と捉えがちです。しかし、歴史を紐解くと、主に診療所の開業医の利益を代表してきた日医と、病院の利益を代表する団体との間には、時に利害の対立がありました。
その結果、病院団体として「日本病院会(日病)」や「全日本病院協会(全日病)」といった、日医とは別の有力な組織が設立されたのです。
診療報酬、病床規制、働き方改革——。これらの重要な政策テーマにおいて、診療所と病院とでは、その立場や利害が異なります。医療政策とは、決して一枚岩の総意ではなく、こうした多様なステークホルダーによる複雑な交渉と力学の末に生み出される「作品」なのだと理解しました。これからは、医療関連のニュースを見る目も、少し変わりそうです。
「現在」は「過去」の積み重ねであり、「政策」は多様な「利害」の調整の末にある。初日に学んだ大きな枠組みに、今日は「歴史」と「政治」という、生々しくも重要な視点が加わりました。明日も、この知的な探求を続けていきたいと思います。