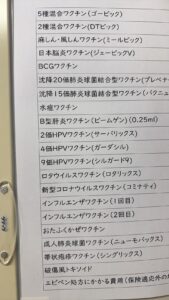リーダーシップの原点を求めて
こんにちは、坂口公太です。
医師として、また地域医療の担い手を育てる立場として、日々「リーダーシップとは何か」を自問しています。
そんな中、先日5月17日(土)にグロービス経営大学院で開講された「中国思想に学ぶリーダーシップ」という講座に参加する機会を得ました。これが非常に深く、示唆に富む内容でしたので、皆さんにも共有したいと思います。
・なぜ今、中国思想なのか?
現代のリーダーシップ論は、西洋的な合理主義や成果主義に基づいたものが多いと感じます。もちろんそれらも重要ですが、多様な価値観が交錯し、複雑な人間関係の中でチームをまとめ、地域社会に貢献していくためには、もっと根源的な人間理解や徳性に基づいたアプローチが必要ではないか、と常々考えていました。
そうした問題意識から、数千年の歴史を持つ中国思想、特に孔子を中心とする儒教の教えに、現代にも通じるリーダーシップのヒントがあるのではないかと期待して参加しました。
孔子の「知」と「仁」~信頼と段階的な愛~
講義の中で特に印象的だったのは、孔子の説く「知」と「仁」の概念です。
私たちが普段「知」というと、知識や情報を多く持つこと、いわば客観的なデータに基づいた理解を想起します。アリストテレスのドクソグラフィー(学説誌)が科学論文の原型であるように、西洋的な「知」は分析的・客観的です。
しかし、孔子の言う「知」は、それとは異なり、他者からの「信用」を獲得することと不可分であると学びました。リーダーが周囲から信用されて初めて、組織や人間関係の秩序が保たれるというのです。これは、患者さんや多職種、地域の方々との信頼関係なしには成り立たない私たち医療者にとって、非常に重要な視点だと感じました。
また、「仁」という概念。これは一般的に「愛」と訳されますが、その本質は「思いやり」や「情愛」であり、孔子はこの言葉に思想的な深みを与えました。
「仁」の実践には段階があり、「大学」で説かれるように、まず自らを修め(修身)、次に家庭を整え(斉家)、それが国を治めること(治国)、そして天下を平らかにすること(平天下)に繋がっていく。この「愛を広げていく」という考え方は、まず自分自身を律し、身近な人々との関係性を大切にしながら、より大きなコミュニティへと貢献の輪を広げていく医師のあり方と通じるものがあります。全ての人を等しく愛すというキリスト教の隣人愛とは異なる、この段階的なアプローチは、現実社会でリーダーシップを発揮する上で示唆に富むと感じました。
・「恕」と「勇」~日本文化に根付く思想と、未来への実行力~
「己の欲せざるところ、人に施すこと勿れ」という「恕(じょ)」の精神。
これは、「自分だったらどう感じるか」を常に考え、他者を尊重する姿勢であり、まさに患者中心の医療の根幹です。日本には「人に迷惑をかけるな」といった消極的な規範(「電車の忘れ物が取られない」文化など)は根付いていますが、一方で「積極的に〇〇せよ」という「作為の教え」が弱いのではないか、という指摘もありました。
「シルバーシートを積極的に譲る人が少ない」という例えは、日常で感じる場面でもあり、医療現場においても、より積極的な関わりや声かけの重要性を再認識しました。
・そして、「勇」。
日本では「危険を恐れない心の強さ」(桜のような潔さ)が強調されがちですが、中国古典における「勇」は、それに加えて「退くべき時は退きつつも、最終的に結果を出せる実行力」、すなわち松のような「しぶとさ」をも意味すると学びました。
これは、困難な状況に直面しても諦めず、粘り強く最善を尽くす医療者の姿、特に長期的な視点で地域や患者さんと向き合う総合診療医に必要な胆力に通じるものだと感じ入りました。
・学びをどう活かすか
今回の学びは、私が島根で取り組んでいる総合的な能力を持つ医師の養成事業においても、非常に示唆に富むものでした。単に知識や技術を教えるだけでなく、人間としてのあり方、他者との関わり方、そして困難に立ち向かう精神力をどう育むか。中国古典の叡智は、そのための豊かな土壌を与えてくれるように感じます。
これからも、東西の知恵を柔軟に取り入れながら、地域医療に貢献できる、人間味あふれる医師の育成に努めていきたいと思います。
皆さんも、日々の忙しさの中で、ふと古典に触れてみてはいかがでしょうか。時代を超えた普遍的なメッセージに、新たな発見があるかもしれません。