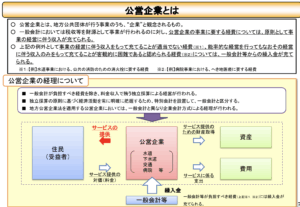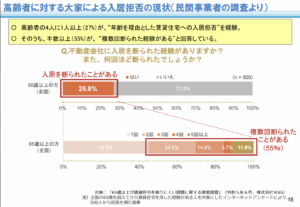GRIPS研修2週目の月曜日、本日は国際医療福祉大学の石川光一先生による「オープンデータを用いた地域把握の実際」という講義でした。これまでの歴史や制度論とは一味違い、膨大なデータを現実に即した「使える武器」として分析する手法を学ぶ、非常にエキサイティングな一日となりました。
DPCデータという「宝の山」
講義の中心にあったのは、多くの急性期病院が国に提出しているDPCデータです。これは、どの病院が、どのような疾患の患者を、どれくらいの数、どのような治療(手術の有無など)で診ているかという、病院の診療実態が詰まった「宝の山」です。
石川先生が開発・公開されているTableau Publicのサイトでは、この複雑なデータが直感的に理解できる形に可視化されており、実際にツールを操作しながら、自分の関心のある地域や病院の姿をリアルタイムで分析することができました。
データで描く、病院の「個性」と「戦略」
特に印象的だったのは、このオープンデータを用いた具体的な分析手法です。
病院機能の客観的な把握:
MDC(主要診断群)別の患者数を見れば、その病院が幅広い疾患を診る「総合病院」なのか、特定の分野に特化した「専門病院」なのかが一目瞭然になります。
SWOT分析による戦略立案:
ある疾患における、2次医療圏内での「占有率(シェア)」と「症例数」をマッピングすることで、各病院の強み・弱みを客観的に分析できます。これは、病院が今後どの分野に注力し(積極的攻勢)、どの分野で他院と連携すべきか(差別化・防衛)を考える上で、極めて強力なツールです。
需給ギャップの未来予測:
将来の人口推計と現在の受療率を掛け合わせることで、地域ごとの「将来の医療需要」を推計できます。これを現在のDPCデータ(供給)と比較すれば、例えば「2035年、この医療圏では心不全の患者数が94%増加するが、供給体制は追いついていない」といった未来の課題が、具体的な数字として浮かび上がってきます。
光と影:データ活用の注意点
一方で、この強力なDPCデータにも限界があることを学びました。DPCに参加していないへき地の中小病院などの実態は、このデータだけでは見えてきません。そうした「光の当たらない」部分を、全ての病院が提出する病床機能報告などの別のデータで補い、複眼的に地域を評価する必要性を痛感しました。
本日の講義は、ともすれば肌感覚や経験則で語られがちな地域医療の課題を、誰もがアクセスできるオープンデータという共通言語の上で議論することの重要性を示してくれました。このデータ分析の視点は、私の研究である「へき地公立病院の経営」を考える上でも、間違いなく大きな武器になると確信しています。